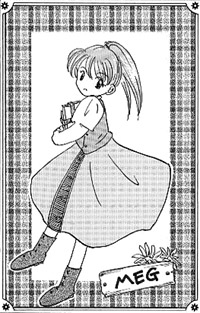|
それは、正式には依頼ではなくて、単なる友達からの頼まれごと、というやつだったかもしれない。ぼくは何の気なしにそれを引き受けて、でも、その事件(と言うほどのものではない)が解決(って言うのも何だか変だけど)した時、これはぜひ、ぼくの事件簿に記録しておかなくっちゃ、と思ったんだ。
あれはちょうど、三月の真ん中へんで、建物の間からのぞく空がヴァージルの持っている精霊石みたいな淡い水色に見える、春の始めの季節だった。
その日はエヴァレット先生の用事も、探偵協会の依頼もなく、相棒のチビも姿を見せないので、ぼくにしては珍しく一人で裏通りをふらふら歩いていたら、聞き覚えのある声がぼくを呼んだ。振り向いたら、それはやっぱり裏通りのアパートに住んでいるクレスだった。
クレスと知り合ったのは、そんなに前のことじゃない。『落とした日記』事件の後、キャロルとつき合うことになったケインに、クラスメイトだって紹介された。ちょっと遠回りな知り合いだけど、友達には違いないし、コウユウハンイが広いのは探偵としても大事なことだって先生も言ってたしね。
そんなわけで、クレスが声をかけてきたのも、道で友達とすれ違ったときの当たり前のあいさつで、それがこれから書くような出来事にまでなるなんて、ぼくは思ってもみなかった。
「エリック! ちょうどよかった。今キミに会いに行こうと思ってたんだよ!」
そう言ってクレスはかけよってきた。
「あのさ、実は頼みたいことがあるんだ。ちょっと他のヤツには言えないようなことで……エリックだったら探偵なんてやってるし、みんなに言いふらしたりからかったりはしないと思ってさ」
もちろん! とぼくは力いっぱいうなずいた。クレスは大事な友達で、その友達の力になれるなら当然のことだし、何より探偵として信頼されるっていうのが、ぼくにはとても嬉しかった。
そして、アパートへ向かう間に、クレスが話してくれた『依頼』はだいたいこんな感じだった。
ん〜、最初っから話すと……そうだなぁ。オレが通ってる学校のさ、女子クラスにメグって女がいるんだけど、そいつ、兄弟が男ばっかりなもんだからやけにさっぱりした男らしい性格しててさぁ、女子クラスのリーダーみたいな感じで目立つし、ちょっと女の子いじめただけです〜ぐ飛んできてつっかかってくるしで、おれとそいつ、いっつもケンカばっかりしてたんだ。
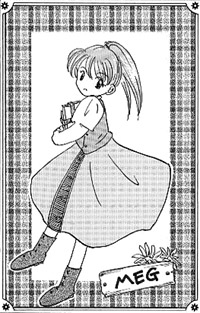
……それで……、ひと月くらい前なんだけど、オレと友達三人で雑貨屋の前を通りかかったら、あいつが買い物してるのが見えたんだ。オレ達気づかれないように中を見てたら、あいつさぁ、ピンクのリボンなんか買ってたんだ。いつも後ろでくくってる髪に結んでもらって鏡見て、それをほどいて本の間に大事そうにはさんで店を出てきたから……オレ達つい、「男女のくせに、リボンなんか買ってど〜すんだよ〜」って、いつもみたいにからかったんだ。そしたらあいつ、いつもみたいにつっかかってこないで、「悪かったわね! しょうがないじゃない、あたしだって好きでこんな……!」って言って、走って行っちゃったんだよ。
オレ……いつもと違う怒り方だったから、さすがに謝った方がいいかもって思ってたんだけど、なかなかきっかけがつかめなくて。五日くらいして……その時メグが落としていった本とリボンをオレ拾ってたから、それ持って謝りに行こうとしたら、あいつ、学校休んでて。次の日、メグが大通りで馬車にはねられてケガしたってウワサを聞いたんだ。オレもうびっくりして……!
情報通のヤツに詳しく聞いたら、命には別状なくて、でも足のスジがどうかなっちまって、今までみたいに歩くことはできないかもしれないって……。あのオテンバには辛いだろって思ってたら、あいつ、それからもう何週間も学校に出てこないんだ。よっぽどショックだったのかとか、まだケガが直りきらないのかとか色々心配なんだけど、何て言って見舞いに行けばいいのかわからなくて……。
そこでさ!エリックに頼みたいんだよ! メグに、あの時の落とし物と、ちょっとしたものを届けて欲しいんだ。何て言うかさ、元気出して欲しくって。
………頼んでも、いいか?
そんなわけで、クレスはぼくの依頼人になった。クレスの部屋で手渡された届け物は、紙袋に入った本と、大人の手のひらにならすっぽり収まってしまいそうな小さな植木鉢。白い布とピンクのリボン(これがメグのリボンなんだろう)で包まれたその鉢に植えてある植物に、ぼくは見覚えがあった。細く長く延びた葉っぱ、折れてしまいそうなか細い茎の先にぶら下がった白い花。たしか、スノードロップとかいったっけ。「待雪草」なんてミヤビな呼び名もあるかわいい花だ。 これを…女の子を、元気づけるために。ほんとに小さくて軽い植木鉢だけど、それを預かる責任は重大だ。ぼくはがぜん、やる気になった。オッケー、ぼくにまかせてよ! 必ずメグに、この花を届けるから!
そう言うとクレスは、安心したように笑ってくれた。ぼくは通りに駆けだして行った。
探偵協会前のゲートを抜けて商店街に出る。相変わらずすごい人出だ。新聞スタンドの前に店を広げて、あやしい像や変なヒモを売りつけてくるおじさんにつかまらないようにはじっこを歩いて大通りに出ようとした時、イキナリ後ろから誰かに体当たりをされた。
「じゃまだガキ!!」
「うわっ!?」(がしゃん!)
「誰かそいつを捕まえてくれ────」
あの後ろ姿は!最近ここらへんで仕事をしてるってウワサのスリのシルバー!
次の瞬間、ぼくの体は勝手に動いてパチンコを構え、エリックスペシャル・クロロホルム弾がヤツの後頭部にサクレツした!
ぐひゃぁ〜、と変な声を上げて、スリは地面に倒れ込み、後ろから追いついてきた被害者や通行人がそれを取り囲んだ。なんたってクロロホルムだし、あれだけ人数がいれば逃げられることもないだろう。倫敦は今日も平和だぜ………って、あれ?鉢植えはっ!!?

それこそ、後頭部を殴られでもしたようなショックだった。鉢植えは、ぼくの足元にあった。砕けた鉢、散らばった土、ぐったりとしたかわいそうな植物。のどの辺りにぐっと、熱い固まりがふくれあがった。クレスの気持ちが込められた贈り物が……。失敗……しちゃった………。友達として、探偵として、ぼくを信頼してくれたクレスに済まない気持ちでいっぱいになって、なんだか泣きたいような気分だったけど、人でいっぱいの大通りでは、そういうわけにもいかなかった。ぼくはしゃがみ込んで、土の間にむき出しになったスノードロップの根っこにそっと触れた。よく見ると、茎は折れていない。球根も無事みたいだ。
(まだ、だいじょうぶ。)
スノードロップが、そうささやいたみたいだった。ぼくはとっさに、ヴァージルの白い顔を思い出した。そうだ! ヴァージルなら、きっとこのかわいそうなスノードロップを助けてくれる!ぼくはかばんからハンカチ(と呼ばれていた布)を取り出して、それに根っこと茎を傷つけないようにしてスノードロップをそっとのせた。少しの間、これでがまんしてね。
ぼくは、裏通りへと引き返して行った。
開発地区の奥の長い長い階段を底まで降りていくと、ヴァージルの住んでいる古いアパートにたどりつく。昼間でも薄暗い、がらくた置き場みたいな玄関を通り抜けて、ヴァージルの部屋のドアを開けると…いつものことなのに、ぼくはやっぱり驚いてしまう。地下鉄よりも低いところにあるんじゃないかって思えるようなアパートなのに、このヴァージルの部屋だけはいつもお日様の光でいっぱいなんだ。建物のすき間をうまい具合にすり抜けて南の窓から差し込んでくる光を浴びて、部屋中の草花たちがおしゃべりしたり、歌を歌ったりしている…そんな気がいつもする。
そしていつものように、一本の背の高い草がお日様の光をかみしめているみたいな感じで窓際に立っていたヴァージルが、驚きもしないで振り向いて、言った。
「……やあ、エリック……」
植物や動物や、目に見えないものたちに等しく向けられるヴァージルの笑顔。ぼくはそれを見ることのできる、数少ない人間なんだ。そのことを、ぼくはちょっと誇りに思っていたりする。
そのヴァージルの無敵の微笑みは、ぼくの中をいっぱいにしていた焦った気持ちや不安な気持ちを全部溶かしてしまった。代わりにぼくの中にあふれてきたのは、期待とあったかい安心感。ハンカチの中のスノードロップも、なんだかほうっとため息をついているみたいに思える。
「あっ、その子は……どうしたの?」
ヴァージルが、ハンカチに包まれたスノードロップに気づいたみたいだ。さすが。ぼくは友達から鉢植えを預かったこと、その鉢植えを落として壊してしまったこと、なんとか約束を果たすためにヴァージルに助けて欲しいことを一気に話した。
話し終わったぼくにまかせてとうなずいたヴァージルは、空いていた鉢に土を入れて、手際よくスノードロップを移し替えてくれた。白い布で下からくるんでピンクのリボンを結ぶと、見た目はほとんどクレスから渡された時と同じになった。ぼくは最後にそばにあった水差しで水をかけてあげたんだけど、やっぱり少ししおれてしまっている。思わず振り返って見上げると、ヴァージルは大丈夫、と笑ってくれた。
ヴァージルの指先が鉢植えの細い茎、白い花びらに優しく触れて、その唇が「さあ、元気を出して……」とささやくと、指先から生まれた白い光がスノードロップを包み込んで………光が消えたときにはスノードロップはすっかり元通り、もしかするとそれ以上に元気に立ち上がっていた。
やった! もう嬉しくて、ぼくは勢いよくヴァージルを振り返った。
「「ありがとう、ヴァージル!」」
ぼくの感謝の言葉は、誰かの細くて透明な声と重なった。うわぁっ……と驚きかけて、ぼくはすぐに納得した。ヴァージルと一緒にいると、こんなことはしょっちゅうなんだ。
声の主は、元気になったスノードロップだった。

「ああ……本当に、ありがとう! わたし、何が何でもメグに会いに行かなければならないんです。クレスがわたしを選んでくれたから……つぼみをやっとつけたばかりのわたしを選んで、こうして花を咲かせるまでメグのためにって大切にお世話をしてくれたから……わたし、クレスのために、メグのために絶対に頑張ろうって思っていたの」
彼女(?)は本当に嬉しそうに、細い葉っぱを揺らしながらいっしょうけんめいにしゃべった。ぼくはクレスだけじゃなく、この子の気持ちも預かっていたんだ…それに気づいて、今さらながらその責任の重さに冷や汗が出る思いがした。
「あっ、リボンも元通り結んでくれたのね。ありがとう、このリボンもとても大切なものなの。このリボンにはメグの─────」
ぼくは、あっと思った。さっきヴァージルに事情を説明した時、ぼくはクレスが話してくれた内容を全部話したりはしなかった。誰かに協力してもらう時でも依頼人のプライベートなことはなるべく秘密にしておくのが探偵の心得……だよね? だからぼくは、クレスとメグの間にあったことや、ピンクのリボンがメグの物だってことなんかは黙っていようと思っていたんだ。
でも、愛しのスノードロップにはそんなぼくの気遣いなんて全然関係ないみたいだった。彼女は二人の事情を全部知っているみたいだし、放っておいたらそれを全部ヴァージルにしゃべってしまいそうな勢いだ。
「あっ、あのっ、」
ぼくはあわててスノードロップのおしゃべりをさえぎった。
「えと……さっきは、本当にごめん!あんなひどいことになっちゃって……。言い訳とかじゃなくって、クレスだけじゃなく、君もそんなふうに思ってたなんて気づかなかった……っていうか、思ってもみなくて……そのこともあやまりたくて……」
ぼくがうまく言葉を見つけられないでいると、首をかしげるみたいに白い花をゆらしてぼくの話を聞いていたスノードロップがくすくす笑いだした。
「ふふっ、いいよ、許してあげるっ。ちゃんと元通りにしてくれたし、ここに来たおかげでこうしてあなたと話すこともできるんだしね」
そうそう、つい忘れがちだけど、こうしてスノードロップと話をしているのもヴァージルのおかげなんだよね。
「本当に……感謝してる。クレスの友達のあなたに、わたしに込められた二人の思いを知っておいてもらえてよかったわ」
スノードロップはそう言って、くすぐったそうに身をふるわせた。でも………あれ?
「ねえ、君に込められた二人の思いってどういうこと? クレスが君を育てたんだから、クレスは分かるけど……もう一人はメグ?だったらどうして……?」
「あれっ、そうだね、メグの思いは正確にはこのピンクのリボンになんだけど……わからないの?」
えーっと、このリボンはメグが雑貨屋で買って落として、それを拾ったクレスがこうして贈り物に結んで……、でも、そのリボンにメグのどんな思いが?
ぼくが思わず首をひねると、横でヴァージルがふっと笑った。かがみこんでスノードロップに話しかける。
「エリックにはわからないみたいだね……。……わからないって言うより、まだ『知らない』って言うのかな……?」
「『知らない』の? なるほど、そうかもね」
……ふたりとも、何だかすごく楽しそうだ。ぼくはちょっとむっとしたけど、それより『知らない』『分からない』事をそのままにしておく方が気にかかる。ぼくがまだ知らない、メグの思い……感情…?
ぼくはえいっと腕組みをして、メグになったつもりでクレスのことを思い出してみようとした。だけど……会ったことのない、しかも女の子の気持ちなんてちっとも分からないよ! それに、そんなぼくのムダな努力はすぐに中断された。
「それじゃ、この子も元気になったことだし、そろそろ出かけようか?」
「え? で、出かけるって……どこへ?」
「もちろん、メグの家に。この子を届けにね。それがキミの『仕事』なんだろう?」
「そ、それはそうだけど……ヴァージルも一緒に?」
「……うん。たぶん大丈夫だとは思うけど、この子がちゃんと『役目』を果たせるか見届けてあげたいんだ」
……『役目』? って、メグを励ますことなんだよね?
なんだかよく分からないけど……考えている余裕はない。
「うん、それじゃ、行こう!」
「……それなら、この子は、君が。」
ヴァージルから受け取った鉢の上で、スノードロップがかすかにふるえた。
後編へ
|